手元供養にはどのくらいの費用がかかるのでしょうか?また、手元供養を始めるためにはどのような手続きが必要なのでしょうか?
この記事では、小さなお葬式の手元供養の費用と申し込み流れを徹底解説します。手元供養に興味がある方はぜひ参考にしてください。
小さなお葬式の手元供養とは?

小さなお葬式の手元供養とは、故人の遺骨の一部を自宅や身に着けるアクセサリーなどに納めて、身近に供養する方法です。
お墓や寺院に行く手間や費用がかからず、故人をいつでも感じることができるというメリットがあります。
手元供養の方法は大きく2種類あります。1つ目は遺骨をそのまま骨壺やペンダントなどに納める方法です。2つ目は遺骨そのものをダイヤモンドや樹脂、セラミックなどへ加工してアクセサリーやプレートなどにする方法です。
どちらの方法も、残った遺骨はお墓や永代供養、散骨などで納骨します。手元供養をする際には、家族や親族の理解を得ることや、保管場所や方法に注意することが大切です。
小さなお葬式の手元供養の費用内訳
小さなお葬式の手元供養の費用内訳を表でまとめました。
| 手元供養の種類 | 費用の目安 |
|---|---|
| 骨壺 | 数千円~数十万円 |
| アクセサリー(ペンダント・ブレスレットなど) | 数千円~数十万円 |
| プレート(遺骨を加工して作るもの) | 数万円~数百万円 |
| ダイヤモンド(遺骨を加工して作るもの) | 約50万円~250万円 |
| 納骨先(お墓・永代供養・散骨など) | 無料~数百万円 |
以上のように、小さなお葬式の手元供養の費用は、選ぶ種類や素材によって大きく異なります。予算や故人の希望に合わせて、最適な手元供養品を選びましょう。
小さなお葬式の手元供養の流れ
小さなお葬式の手元供養の流れを表でまとめました。
| 手元供養の種類 | 手元供養の流れ |
|---|---|
| 骨壺 | 1. 骨壺を注文する 2. 骨壺が自宅に届いたら、骨壷から遺骨を取り出し、骨壺に納める 3. 骨壺を遺影と共に飾る 4. 残った遺骨は納骨先(お墓・永代供養・散骨など)へお納めする |
| アクセサリー(ペンダント・ブレスレットなど) | 1. アクセサリーを注文する 2. アクセサリーが自宅に届いたら、アクセサリーに遺骨を入れる 3. アクセサリーを身に着ける 4. 残った遺骨は納骨先(お墓・永代供養・散骨など)へお納めする |
| プレート(遺骨を加工して作るもの) | 1. プレートを注文する 2. 遺骨を送る 3. プレートが自宅に届いたら、飾る 4. 残った遺骨は納骨先(お墓・永代供養・散骨など)へお納めする |
| ダイヤモンド(遺骨を加工して作るもの) | 1. ダイヤモンドを注文する 2. 遺骨を送る 3. ダイヤモンドが自宅に届いたら、アクセサリーに加工するか飾る 4. 残った遺骨は納骨先(お墓・永代供養・散骨など)へお納めする |
以上のように、小さなお葬式の手元供養の流れは、選ぶ種類によって若干異なります。どの方法も、残った遺骨は別途納骨する必要があります。
手元供養を始める前に、家族や親族と話し合って最終的な納骨先を決めておくことが大切です。
小さなお葬式の手元供養のメリット・デメリット
小さなお葬式の手元供養には、メリットとデメリットがあります。この記事では、それぞれについて解説していきます。
小さなお葬式の手元供養のデメリット
■家族や親族の理解を得られない場合がある
手元供養が選ばれるようになったのはここ10年ほどのことで、比較的新しい供養の形であるといえます。そのため、反対する家族や親族は少なくありません。
特に、日本では「遺骨はお墓に納めるもの」というイメージが強く、年配の方ほど手元供養に抵抗を感じる傾向です。
こうしたことを踏まえると、家族や親族の理解を得られないケースがあることを想定したほうがよいでしょう。その時は強引に進めず、ご自身や遺族の気持ちを丁寧に伝え、しっかりと話し合いをした上で決めることが大切です。
■紛失するリスクがある
身に着けるタイプの手元供養品は、紛失リスクが高くなります。例えば、携帯できるミニ骨壺を入れたバッグを置き忘れたり、遺骨を入れたペンダントの鎖が切れて知らない間に紛失してしまったりすることもあるでしょう。
また自宅保管のタイプでも、洪水や地震などの災害で失ってしまう可能性はゼロではありません。こうしたリスクがあることを知った上で、責任を持って大切に保管し続けることが必要です。
■骨壺のカビなどに注意するため保管場所に気を付ける
遺骨にカビが生えるトラブルは多く、保管場所には注意が必要です。カビは高温多湿の環境を好むため、お風呂場やキッチンの近くやクローゼットの中などを避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所を選びます。
また保管容器の内と外で温度差が生じると、結露が発生してカビの原因になるでしょう。エアコンの風が直接当たる位置などは、冷房を稼働させた際に温度差が生じて結露しやすくなるので注意します。
保管場所以外の対策として、しっかり密閉できる容器を選ぶのがおすすめです。空気が遮断されて結露が生じにくくなる上、カビの胞子の侵入も防げるでしょう。
小さなお葬式の手元供養のメリット
■故人を身近に感じられる
遺骨を自宅で保管することで、常に故人をそばに感じることができます。手元供養を選択された方の中には、「暗いお墓の中ではかわいそう」といった意見もあり、故人とのこれまでの関係性を大切にされる方にとって大きなメリットとなります。
■遠方へ出向かずに供養ができる
引っ越しや、体調が優れない場合などに、お墓や寺院などに納骨している場合は出向くことが難しくなることもあります。手元供養なら、距離や時間を気にすることなく供養ができます。
■保管場所に困らない
遺骨を納める骨壺やアクセサリー類はコンパクトなものが主流であり、保管場所に困らないこともメリットです。例えば、ミニ骨壺と呼ばれる骨壺は、棚やテーブルの狭いスペースにも置けるでしょう。
また、ペンダントのように身に付けられるものや、一般的な住宅のインテリアになじみやすいプレート型のものもあります。保管場所に困らないことは、将来的に引っ越しをしたり高齢者向けの施設などに移ったりすることを考えたときにも安心です。
手元供養する前に決めておくこと
手元供養をする前に決めておくことがあります。それは、最終的にどこにどうやって納骨するかということです。手元供養の品は、紛失や破損、盗難などのトラブルに合う可能性があります。
また、供養していた方が亡くなったり、それを継ぐ方がいなくなった時はお墓に納骨や永代供養・海洋散骨します。
残された方に負担が大きくならないように、生前に夫婦や親族で話し合っておくことが大切です。手元供養を始める前に、最終的な納骨先を決めておきましょう。
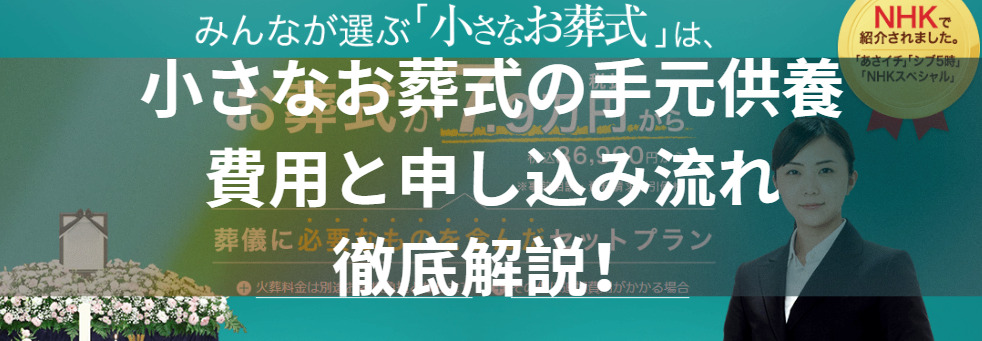
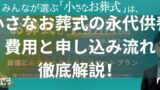
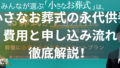
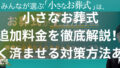
コメント